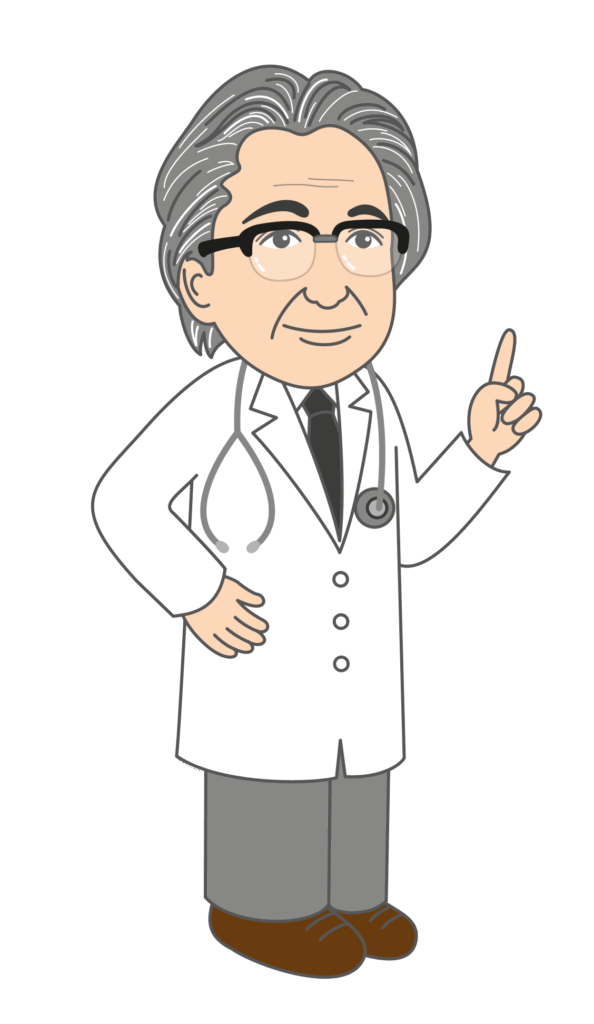第八回 皮膚血流と脳血流
汗をかくこと、皮膚の活動を行うこと、こういう様々が脳の血流にも関与しているらしいことが分かっています。手足を動かすこと、皮膚を刺激することで、脳の血流が増えます。場所は違いますが口の中の粘膜をこすったり刺激することや歌うこと話すことで、唾液や脳の血流が増えます。手足・口腔などの刺激が脳の血流を増やすことが知られています。脳血流が増えるのみならず、前脳基底核にあるマイネルト核の働きが活発になり、脳内のアセチルコリンの活動が賦活され、アセチルコリン作動性の神経が活発になります。例えで言いますとアルツハイマー型認知症の治療薬である「アリセプト」などの薬はアセチルコリンの分解を遅らせるといいますか、そういう作用があるわけです。それで認知症に効果が期待できるわけです。
実際マイネルト核から脳の大脳皮質全体に神経が伸びています。マイネルト核が活動すると脳全体の血流が増えて、脳神経を活発にさせるアセチルコリンが増えることになります。この発見は1989年北大の佐藤先生によるものです。脳内自律神経システムの一つとして、コリン作動性神経と略称されています。では認知症予防と関連していると考えてよいのでしょうか。答えは大ありです。考える脳である大脳だけではなく、短期記憶をつかさどる海馬や、感情の脳である偏桃体、においを感じる嗅球とつながっています。マイネルト核の機能低下は記憶や考えること、においや感情の低下と大いに関係してくるのです。意欲とも関係してきます。繰り返しますが、手足を動かすこと、さすったりすることで、脳の活動が活発になるのではないかということです。体を動かすことで脳が活動するのですから、動かさにゃ損です。動かしてばかりでは脳も疲れますので、睡眠や休息も適度に必要になります。

アルツハイマー型認知症の方では、マイネルト基底核の神経細胞脱落が見られます。記憶だけではなく、意欲が低下したりすること、においの感覚も低下することが関連してくると考えられます。
メカニズムは異なりますが、パーキンソン病の方でも初期からにおいの感覚が低下します。レビー小体病の方も同様です。予防のためにハーブを利用したアロマ療法が昔から行われています。いろいろな量販店でハーブのスプレー商品を扱っていますのでご自分に合った心地よい香りを楽しんだらよいとおもいます。ミントやローズマリー・ラベンダー・タイム・レモングラス、大体こういうところが主だったところです。アロマ療法の前提は、鼻炎蓄膿症を治療しておくことと禁煙することです。
手足を動かすこと、においを研ぎ澄ますことは脳を守ることでもあります。「指圧の心は母心、押せば命の泉わく」も、それなりに正しい部分があります。そんなに外れた言葉ではないと思います。デジタルのご時世ですが、まず体を動かすところから健康づくりが始まります。