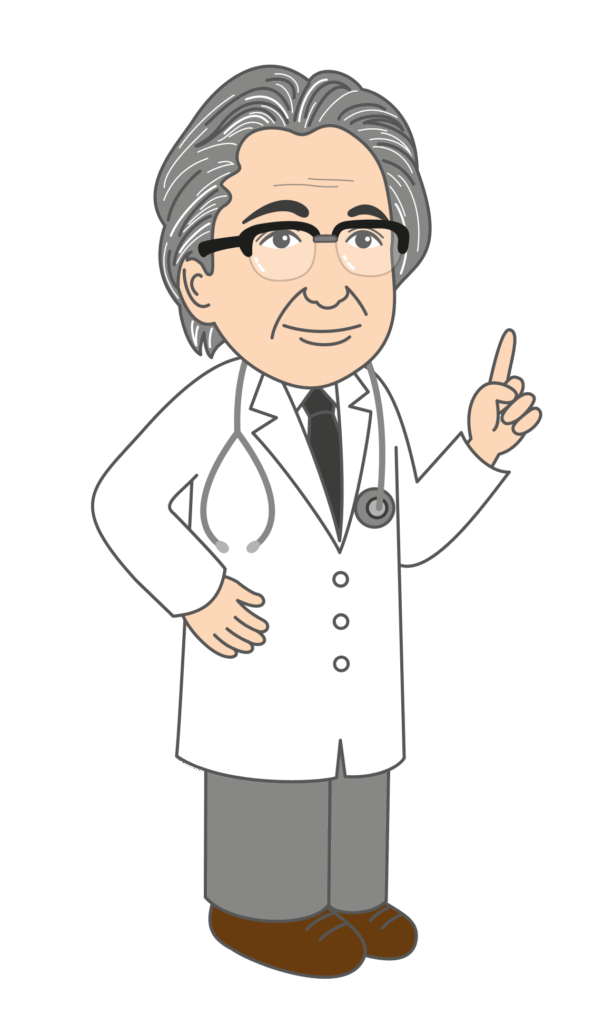第十一回 腸脳相関
今回は脳と腸の深い関係を説明します。脳や脊髄から交感神経と副交感神経がでて、内臓の機関を神経支配します。ところがどうしてもわからないことだらけだったのですね。副交感神経の代表格が迷走神経です。顕微鏡が発達していない時代にはどんなに名の知れた有名な解剖学者でも末端まで追いきれない神経として命名されたのが迷走神経です。どこから出ているのかはわかるが、行きつく先が分からない、だから迷走、そんな時代がありました。なので、自律神経といえば交感副交感の二つが有名で、内臓からの情報を脳や脊髄に送るという、求心性内臓神経という三つ目の記載はだいぶ後のお話です。この内臓神経は痛みの情報を交感神経に沿って上行して伝え、痛み以外の内臓情報は副交感神経に沿って脳脊髄に伝達します。自分自身医学教育を受けたころにこういう明快な記載はなかったと思います。
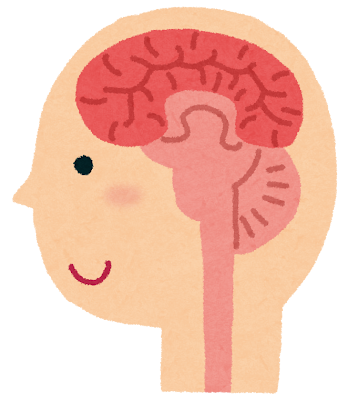
腸の感覚を、神経を介して伝えていくのです。痛みはわかりやすい表現ですが、例えば「おならが溜まった、うんちが出そう」の感覚について腸の神経はガスとうんちをどのように区別しているのでしょうか。腸には二種類の神経叢(しんけいそう)が分布していて、蠕動(ぜんどう)運動(うんちを肛門に送り出していく)や消化液分泌など、脳の支配がなくても何とかやりくりできるそういう内臓が腸です。それに加えてホルモン分泌の働きや、腸内細菌叢の働きで、神経の動きがコントロールされているという、腸が脳をコントロールしているという「腸脳相関」が脚光を浴びるようになりました。
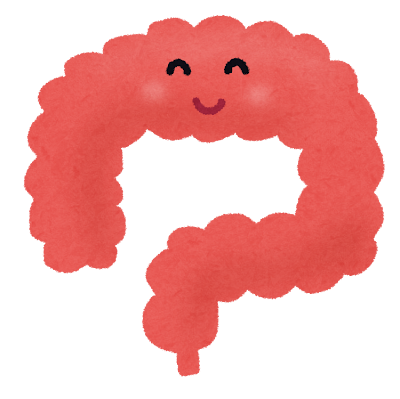
ホルモン分泌の代表格が胃から分泌されるグレリンです。空腹になって胃袋がカラになるとグレリンが分泌され(空腹のときに胃がグーグーなる)て、脳の視床下部の摂食中枢が刺激されて、食欲が増し摂食が促されます。
腸内細菌も大事な役目を負っています。どんな腸内細菌が多いのか、その結果としてどのような腸内代謝物が増えるのか、その結果うつや認知症など多くの神経疾患の発病に関連しているという報告が近年多くなってきました。腸内細菌は寿命にもかかわるという報告が多く、京都の丹後地区の寿命の長さと関連があるようです。
腸の自律神経、腸そのもの、内臓や脳を守るためにどうしたらよいのか?食べ方で言えば偏食せずに様々な食品をバランスよく食べること。腸内細菌の餌となる食物繊維やオリゴ糖をたくさん食べること。ヨーグルトなどの乳製品や発酵食品をとることで有用な腸内細菌が増えるなど、多くの提案がなされてきました。もちろん適度な運動が必要ですし、睡眠の質を上げることも大事です。抗生剤は有用な細菌を減らすことがあります。
腸は、栄養を吸収するだけではなく、心と脳の健康に大いに関係があるのです。脳と腸の深い関係をご理解ください。まずは便秘を避けることが第一歩です。