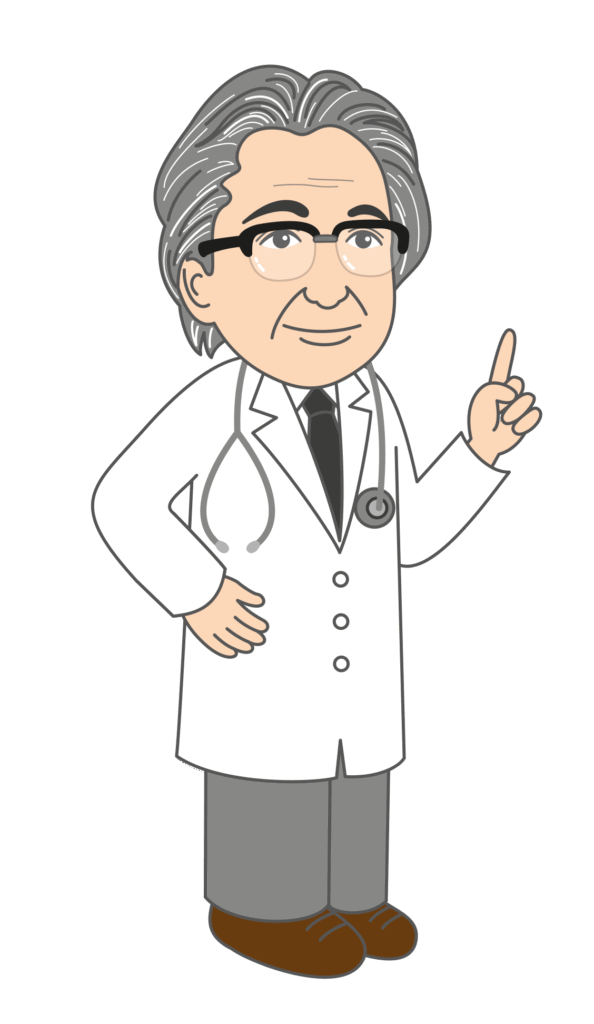第十二回 子供の起立性調節障害
子供さんに多い起立性調節障害について、自分は最近まで門外漢でした。ここ数年片頭痛の患者さんを多数診察するようになってから、小学生中学生に、簡略に言えば「朝起きられない」子供さんが結構おられるということに、(遅まきながら)気づきました。朝に起きられないのではなく、「朝に目は覚めてはいても、身体を起こし、動き出すとしんどくて、学校にいけない」というのが、子供さんたちの訴えの核心であると気づくまで、私にはしばらく時間がかかりました。症状は午前中に強く昼から夜に改善するために、「不登校」のレッテルを張られることがあるのです。実際にはいじめなどのメンタル面から「不登校の子」もいるかもしれませんが、片頭痛で通院している大多数の子供さんは、いろいろ夏休みはあれしたいこれしたいと話してくれますので、じいちゃん年代としては安心してほっとすることが多いです。
起立性調節障害の症状は、血液の循環調節がうまくいかなくて起こります。子供さんに多いのは、身体成長過程であること、それに加えて生活習慣や自律神経、睡眠習慣と心理的ストレスが関与しています。朝に起きようとすると重力で血液は足に多く頭に少ない状態(脳の貧血状態)になります。朝に交感神経のスイッチが入りにくいと血圧や脈拍・体温上昇など身体のエンジンがかかりませんし、昼夜逆転の睡眠リズム障害があるとさらに身体が動かなくなります。2020年に「小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善」治療薬が発売されました。小児科の先生にご相談ください。

子供さんの起立性調節障害は、1990年代から増加しています。アメリカの自律神経学会の重鎮のロバートさんは「子供の運動不足・夜更かし・長時間の臥床」を原因として挙げています。例えばですが、宇宙飛行士は微小重力の状態でお仕事をされています。無重力にちかい微小重力状態を別の言葉でいえば「寝たきり」に近いということになります。屈強な宇宙飛行士ですら、地球に帰還した直後には身体能力が極端に下がり、起きて歩くこともままなりません。健康な若者を寝たきりにさせて、10日目に急に起立させると、脈圧(上と下の血圧の差)が極端に少なくなり、心臓を栄養する冠動脈の血流が保てず、頻脈になってしまい、起立性調節障害の症状が出ます。
特に新型コロナ感染症が多くの人々の外出を妨げました。学校閉鎖前後の運動機能調査で、明らかに運動耐用能力が低下した地域が多かったと報告され、それ以後子供さんの起立性調節障害が増えたという報告があります。慢性的な寝たきりは身体の水分を減少させます。点滴をすると元気になるお年寄りや若者が結構います。運動不足は血圧コントロールをやりにくくさせるようです。
わたくしがこの症状に巡りあったのは、冒頭に書きました片頭痛の子供さんに朝起きられない症状が多かったためです。まずは小児科でお問い合わせください。