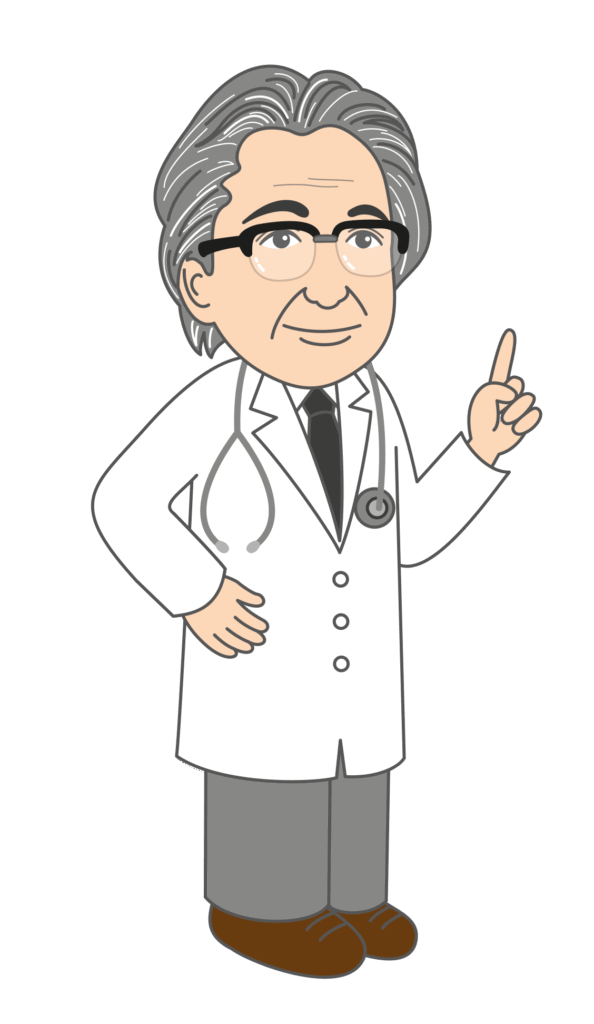第四回 緊張型頭痛
緊張型頭痛についてお話します。平たく言えば「肩こり」です。肩こりと申しましても、一般的には後頭部や頚の付け根から肩関節までの広い範囲を指します。頚の付け根は頭がい骨と背骨を支える部分で、肩関節は上腕骨や肩甲骨・鎖骨と関節を形成しています。頚の付け根とのど元は頭を支える脊椎の存在のみならず、手足につながる神経の束である脊髄、そして食事・呼吸・発声をつかさどる生命維持に重要な部位です。肩関節はとても動く範囲が広く、人間にとって大事な手や腕の動きをサポートし、孫の手も借りますが背中を掻くことができます。ところが頚の関節は頭を固定することのほうが重要で、ろくろ首のように後ろを見ることはできません。そこで、私は肩関節の痛みを主にする「肩こり」と、頚すじの後ろの痛みを主とする「頚こり(くびこり)」をごっちゃにしないほうが良いのではないかと考えています。もちろん筋肉のつながりや関節運動の連携がありますので、まったく別のものという考えも違うと思います。肩関節の痛みは整形外科の先生にご相談ください。
片頭痛の方の7割程度に「肩こりか頚こり」が合併します。片頭痛や緊張型頭痛の誘因として運動不足、遅寝遅起き、スマートフォンやパソコンの長時間視聴での悪い姿勢(いわゆるスマホ頭痛)、ストレスなどの共通要因があります。緊張型頭痛は、かつては働き盛りに多い頭痛でしたが、近年はスマホ頭痛が増えて若年者にも多い頭痛になりました。スマホ頭痛の主な原因は「頚・肩への過剰な負担」と、それによる「筋肉の緊張」「血行不良」で、スマホやパソコンを見るときの姿勢・環境が大きく関係しています。スマホ画面を見るときのうつむき姿勢や、前かがみでのパソコン作業は頚や肩に大きな負担がかかり、筋肉の緊張による血行不良を招きます。ほかにも、ブルーライトによる体内リズムの乱れ、画面の見過ぎによる眼精疲労なども頭痛の原因となります。スマホ頭痛の症状には、頭全体の締め付けられるような痛みが特徴で、筋肉の緊張とそれによる血行不良が原因です。スマホ頭痛を防ぐためには、適切な姿勢でスマホやパソコンを使用すること、適度な運動をすること、十分な睡眠をとることが大切です。運動療法については日本頭痛学会のホームページに一般の方へのお知らせ欄があり、頭痛について知る項目から頭痛体操をクリックしていただけますと予防体操について詳しい解説が掲載されています。内服治療やマッサージ、整体治療なども有効です。

たかが肩こりかもしれませんが、高度になりますと、寝込んだり吐いたりすることもあります。筋膜の痛みのポイントの増加が難治化を招きますし、痛み神経が敏感になり脊髄後角や三叉神経核の痛覚過敏を引き起こすと、片頭痛並みの重症頭痛になってしまいます。たかが肩こりではありません、されど肩こりです。肩回し肩上げのストレッチを毎日してください。