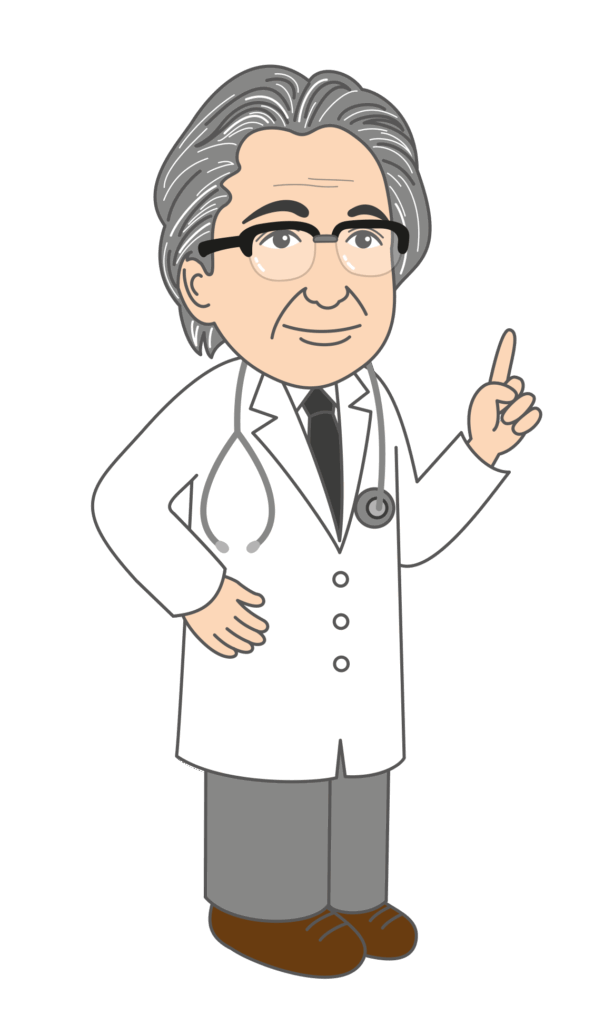第一回 睡眠と認知症
睡眠と認知症は大いに関連があります。なぜかと申しますと、睡眠、特に深睡眠の時に蛋白質(アルツハイマー病の原因のアミロイドβなど)が、グリンファティックシステムを通して排泄されるという理論が報告されました。この理論には反論もあるのですが、魅力的な学説です。一般的に極端な睡眠不足は「うつ病」や、睡眠不足から誘発される生活習慣病が「認知症」を誘発し得ることから、不眠が認知症を増やす、転じて、睡眠薬を飲むことで認知症が増えると信じられるようになりました。半分正解半分間違いというところでしょうか。
睡眠薬の歴史です、一番古いブロモバレニル尿素(いわゆるブロバリン)は保険医療では使われませんが、今でも有名な市販薬に含まれています。次いで開発されたバルビツール系は耐性がつよく大量に飲まないと効果が減弱するため、薬物中毒事故が相次ぎ、1960年ころには使われなくなりました。限定的に抗てんかん薬などで使われています。そして脚光を浴びて登場したのがベンゾジアゼピン系睡眠薬(BZD系と略)です。BZD系は睡眠薬以外にも精神科疾患の治療薬として使われています。GABA(ギャバ)受容体に作用し、とても効果が高く良い薬ではありますが、転倒骨折を誘発したり、耐性や依存性もあり得ますので、注意が必要です。BZD系は単剤かつ少量であれば認知症を誘発することは少なくあまり重大視しないほうが良いのでないかといわれていますが、BZD系で効果が長く続くタイプや急速に効くタイプでは注意が必要です。

そしてメラトニン系やオレキシン系の睡眠薬が遅れて開発されました。ノーベル賞候補といわれている柳澤先生の発見された、覚醒を維持するオレキシン系をブロックする睡眠薬は耐性が少なく依存性がなく自然な睡眠に近い効果で、不眠の方には第一選択と言えます。自然な睡眠に近く、依存性がほとんどないので卒薬しやすいのがメリットです。これらの系統ではあまり認知機能を低下させないといわれております。
睡眠を妨害して認知症を誘発し得る病態は、たくさんあります。筆頭は睡眠時無呼吸症候群です。いびきをかいて無呼吸となり、長い人では1~2分呼吸が止まり、脳と全身が低酸素になります。酸欠になって最悪の環境で夜を過ごし、朝は疲れ切って頭痛がして口が渇いて目が覚めます。血液や酸素の運搬がうまくいかなくなると脳のみならず全身の健康が脅かされることとなります。このように睡眠は、昼に元気で生活できるようにするための、重要な生理活動ととらえてください。今回から数回睡眠がどのように健康を作るのか、特に呼吸はどんなに健康づくりに頑張っているのか、説明いたします。