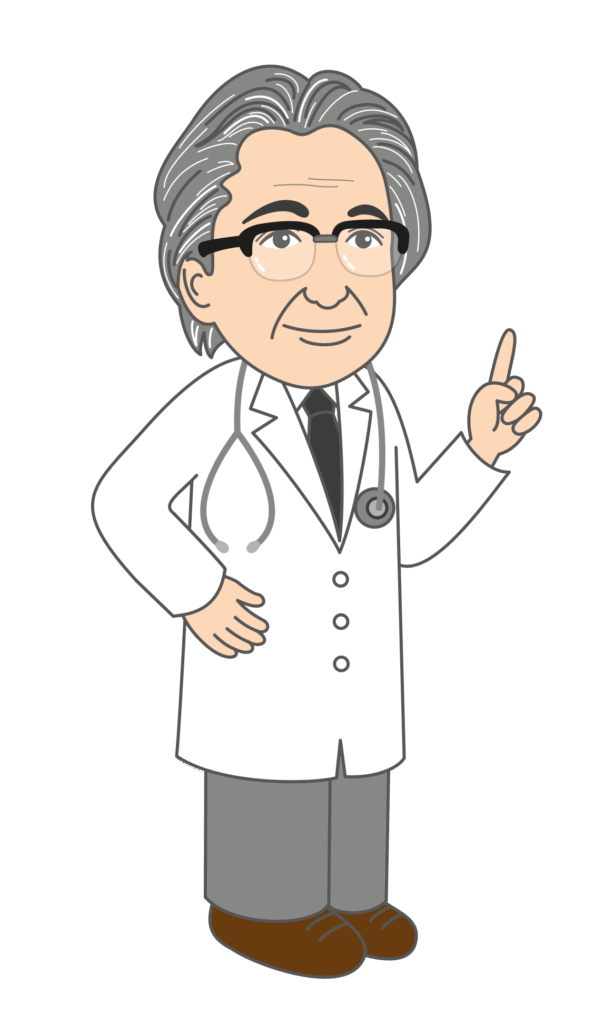第十五回 よく眠れていることと自律神経
前回体内時計について記載し、自律神経の解説をしました。今回は睡眠中の自律神経のお話です。
ざっくり言えば交感神経は「日中に活発な自律神経」です。副交感神経は「夜に活発な自律神経」となります。身体の24時間リズムは、昼は交感神経に、夜の睡眠中に副交感神経が活発になります。この交感・副交感神経の働きはシーソーにたとえられます。どちらかが活発な時にはどちらかがお休みモードになっているのです。通常の場合、どちらも活発とか、どちらも寝ているということはないのです。身体の恒常性を維持することを「ホメオスタシス」といいます、変化を予測し内部環境を変化させ対応することを「アロスタシス」といいます。簡単に説明できませんので、別稿します。
睡眠中に活発なのが副交感神経です。睡眠にはノンレム睡眠とレム睡眠があります。レム睡眠は夢を見る睡眠で、身体の筋肉は休んでいますが、眼だけがきょろきょろしている睡眠です。子育てした方はわが子のレム睡眠を何度も見ていると思います。ノンレム睡眠は寝返りをうったりもしますが、夢はほとんど見ていない睡眠です。寝付くとまずノンレム睡眠で深い睡眠から覚めかけた時にレム睡眠になり夢を見ます。このパターンを一晩に数回繰り返します。朝方になると眠りの深さが浅くなり、ノンレムーレム睡眠のサイクルが短くなり、覚醒します。レム睡眠の時には、交感神経が昼の覚醒しているとき以上に活発になります。その結果夢を見ているときには血圧が上がり、脈は速くなっています。睡眠生理学の先生方はレム睡眠を「自律神経の嵐」と例えることがあります。夢を見る睡眠は朝方に増えるため、夜間高血圧の方や早朝高血圧の方は、朝方に脳卒中を起こしやすく、また心筋梗塞を起こす確率が高くなります。通常夜間は副交感神経が活発ですので、血圧や脈は下がるのが普通なのですが、朝の血圧の高い方は合併症を起こす確率が高くなりますので、かかりつけの先生や循環器科の先生にぜひご相談ください。

睡眠時の姿勢はどうでしょうか?横向き・仰向け・うつ伏せ、どの姿勢が多いのかを調べる機器が進歩しています。身体につけたるウェアラブル機器(例えば時計)やマットに圧力感知センサーを付けて測定できます。ほとんどの人は仰向けか横向きの時間が長いです。年齢とともに横向きの時間が長くなってきます。うつ伏せになると心臓と肺が圧迫されてつらい、仰向けだと睡眠時無呼吸が誘発されていびきと無呼吸をおこしやすい、この二つが原因と考えられています。いびきと無呼吸は、脳や身体の低酸素と血圧上昇、脳の老廃物を流せないなどの悪さをします。睡眠はたかが睡眠ではありません。自律神経の嵐を起こしすぎないようにすること、睡眠は人生の三分の一と心得てください。寝る子は何歳になっても育つのです。睡眠薬よりも睡眠衛生が大事です。次回は寝るための衛生法です。