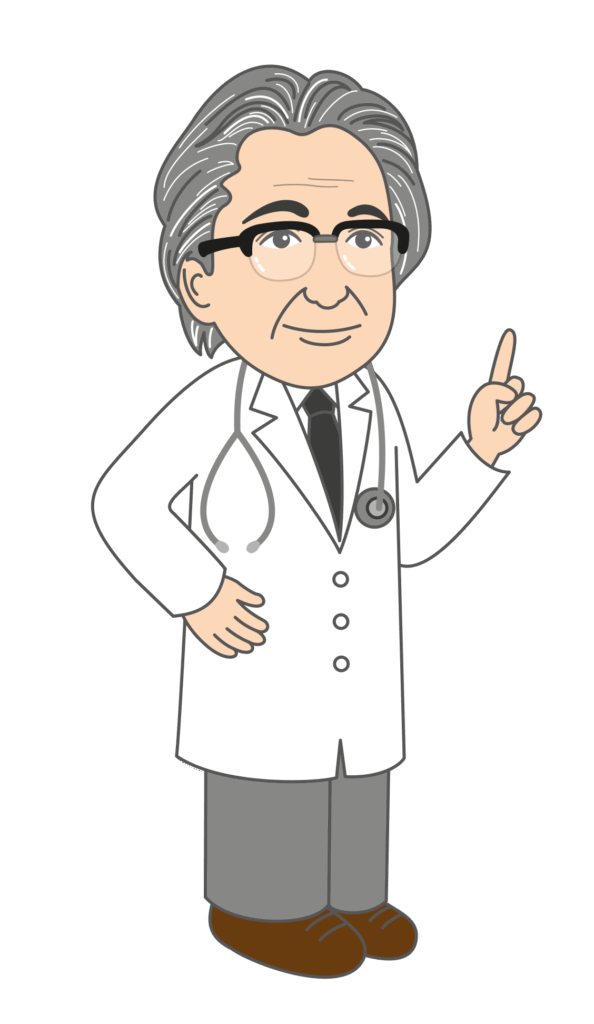第十三回 起立性調節障害2
前回の続きで、朝に頭痛やめまい立ち眩みがして起床しにくい、子供さんに多い起立性調節障害のタイプについて特徴を解説します。多いのは起立直後性低血圧、体位性頻脈症候群、血管迷走神経性失神、遷延性起立性低血圧の4つです。稀な二つを入れて6つです。
まず起立直後性低血圧です。これは起立直後に血圧が著しく低下してしまい、血圧がなかなか回復しません。脳血流の低下により、立ちくらみやめまいなどの症状が出現します。起立後の血圧低下回復までの時間が25秒以上かかることが多いのが特徴です。細かな部分は省きますが、一般的には平均血圧が60mmhg以上なければ臓器血流が低下している状態と評価されます。軽症であれば徐々に血圧が改善し症状もやわらぎますが、起立後数分で逆に収縮期血圧が低下するような重症型の場合には、回復が遅れ脳の虚血に陥り失神する可能性もあります。
二つ目が体位性頻脈症候群です。これは起立に伴う血圧低下はありませんが心拍数の著しい上昇を認めます。その結果ふらつきや倦怠感、頭痛症状が出現します。また、本人は意外にも動悸を自覚していないのが特徴です。
三つめが血管迷走神経性失神です。これは起立中に突然の血圧低下を認めて脳の血流不足が生じ、意識が薄れたり突然意識がなくなったりします。校長先生の話が長い時に女子高生が急に倒れたりするシーンを想像すればわかりやすいかもしれません。また、血管迷走神経性失神は起立直後性低血圧や体位性頻脈症候群を併発する場合があり、併発すると重症型となることが多いです。
四つ目が遷延性起立性低血圧です。これは起立直後には問題ありませんが、継続して立ち姿勢のままでいると血圧が低下し始めるのが特徴です。
以下の二つは極めてまれです。脳血流低下型(起立性脳循環不全型)脳血流低下型は起立後の血圧や脈拍には問題ないのに脳血流だけが低下する状態です。最後に過剰反応型です。これは起立直後の血圧が一時的に異常な高値を示し、めまい症状を引き起こすものです。重要なのは小児科・循環器科のある専門の病院で診断をつけて治療を行うことです。心電図や血液検査などの一般的な検査に加えて、起立試験という血圧測定の検査が行われます。寝ている状態から起立して血圧や脈拍の変動を調べます。この検査は午前中に行う必要があります。

子供さんの起立成長性障害は成長とともに改善することが多いです。まずは水分摂取を十分にすることや食事を三食きちんと食べること、運動は午後の症状の楽な時間帯にすることが大事です。着圧ソックスなどのちょっとした工夫も効果があります。内服薬の効果はありますが、薬がすべてではないのがこの症状の治療を難しくしています。中学生までの方はまず小児科、高校生は循環器科の先生にご相談ください。頭痛が強いときは脳神経系の受診をお願いします。